ブログをはじめて3年で商業出版に至った話
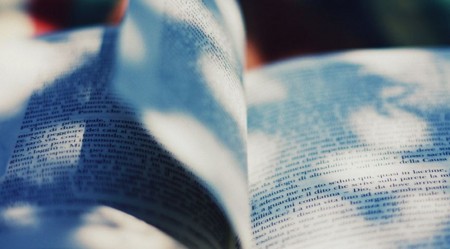
僕がこのブログを始めたのは3年前の3月23日だった。
物書きになりたかった僕は人生最後の挑戦と思ってこのブログを始めたのだ。
何度もやめかけながらも毎日更新し、やがて、たくさんの人に読んでいただける記事がポツリポツリと出たりして、先月には本を出版させていただいた。
そして、みんなに助けてもらって、ブログの読者のかた、高校時代の友人や昔の会社の人たち、クラブの先輩後輩、今の業界の人たちに助けていただいたおかげで、その本の増刷が決まった。
また、出版社の担当の方がおっしゃるには、韓国の出版社4社から翻訳の引き合いもあるという。
みんな~!ほんとうにありがとう!(80年代風ディスコパーティーだ!)
そこで、物書きになりたい、自分の本を出版したいと思っておられる方のために、そこに至った道のりの中で、自分なりに学んだことを共有してみたい。
どうしても、自慢話みたいになる。(ごめん!)
それに、出版に至る道は一本でないことは明らかだから、あくまで、僕の場合ということで、参考になる点だけ心にとめておいていただければと思う。
1.毎日書き続けた
書く時間については人によってさまざまだろうけれど、僕の場合は、毎日朝の5時ぐらいから8時ぐらいまでの間に、毎日、必ず記事を書いた。
物書きになりたいと言いながら、毎日書いていない人も多いはずだ。かつての僕のように。
もう50歳を過ぎていた。
夢を夢で終らせるのか、最後の挑戦をするのか。
僕は最後の挑戦をすることにしたのだ。とにかく、なにがなんでも、毎日書くことで。
そして、書きたいことがみつからない時でも、とにかく書くということが、どれほど書くことについての良い練習になるのか、どれほど自分の考えを深めることになるのかということを学んだ。
2.なにかを犠牲にした
毎日書く時間を捻出するために、犠牲にしたものもある。
そのなかで、もっとも辛かったのは、人付き合いである。仲間たちが楽しそうに飲みに行っているところを横目で見ながら、そそくさと家に帰って、翌朝に備えて、10時には寝た。
友人たちは、飲みに行ってどんな楽しいことがあったか、どんな馬鹿なことをして大笑いしたのか、楽しそうに語っている。
その度に、そんな楽しい時間を共有できなくて、なんの人生かと苦い思いがこみ上げてきた。
しかし、僕は家に帰った。
3.たくさん書くことで、自分の経験のうち、なにがもっとも共有する価値があるのか発見した
ブログにしても、本にしても、自分の体験や考え方の何を、人に訴えたいのか、何を共有してもらうことで、人の役に立つのかをはっきりすることが、もっとも大事なように思う。
そして、それが何かということは、当初から明らかである場合ばかりでもない。
僕は当初、自分が脱サラして商売を始めた時のことをメインに書いていた。今でも書いているが、その体験がもっとも人に役に立つと思い込んでいた。
しかし、本になったのは、会社員時代の失敗の話だった。
つまり、自分の中の共有したいものと、外から見て価値のあるものは、異なる場合があるのである。
それは、たくさん書いて、それを人に見てもらうことによって、はじめてわかることなのかもしれない。
少なくとも、僕の場合はそうだった。
4.誰かが見ている
1年半ぐらい、あまり読まれない時間を過ごした。
正直に言って、僕もPV数を一日に何度も見るような生活を長く続けてきたが、やはり、PV数はひとつの側面にしか過ぎないように思う。
僕のブログのPV数は最高の時で月間50万PVぐらい。現在は20万PVから30万PVぐらいである。
有名ブロガーさんの公表値に比べたら相当見劣りする。
だけど、今の僕の実感は、20万PV~30万PVで充分じゃないかというものだ。
その程度のPVでも、ハフィントン・ポストさんが転載してくださったり、リクナビネクストさんなどに寄稿させていただくようにもなった。
自分が共有すべき体験や考え方のコアを書き続けたら、どこかで誰かが見てくれていて、その人達が必要な人に届ける手助けをしてくださったのである。
そういうことが、結局、出版にもつながっていくように思う。
5.書くべきことと書くべきでないことを理解した
僕は実名で書いている。
書くべきことと書くべきでないことも、毎日記事を書き続けるあいだに学んだように思う。
もし、ゆくゆくは出版したいとすれば、書かないほうが良いことは書かずに我慢したほうがよい。
会社に勤めておられる方は、実名のブログはしない方が良いと思うが、匿名の場合も、いつかそれが自分の発言として紐付けられることを念頭において書いたほうが良いと思う。
6.出版社には広く門戸を開けておく
僕の場合、数社の出版社の方が連絡をしてこられた。
出版社の方々は、それが有名出版社であろうとなかろうと、かなりあいまいな動機で連絡をしてこられるようだ。
最初にそういう話があったとき、僕は大海で漂流するボートから、大型客船を見かけたように狂喜して、アピールした。
その人たちがみんな本をつくってくれていたら、僕はすでに数冊の本を出しているはずであったが、全部途中で霧消してしまった。もちろん、僕は先方の提案にはすべてのるつもりで、必死でいろいろな提案をしたのだが・・・
今回、本を出してくださったバジリコ出版の長廻社長さんは、電光石火であった。
ある日、ブログのカウンターが急増した。だれかひとりの人が過去記事をたくさん読んでいるのだ。
おそらく、それは長廻社長だった。
直後に長廻社長からメールがあり、本を出したい、近々にそちらに行くとおっしゃられた。たまたま、僕はその日、どうしても外せない仕事があり、その日は断ることになった。
せっかく来てくださるというのを断ったので、その翌週、僕は東京に出向いて、長廻社長にお会いした。
その場で、本の趣旨を説明していただき、ページ数と原稿の締め切りを教えてもらった。
そして、社長はこうおっしゃられた。
原稿はまかせると。朱を入れるかもしれないが、最終的には、原稿のすべての決定権は僕にあると。
締め切りは1か月半後。
それまで連絡してこられた人とはおっしゃることがまったく異なっていた。
僕はさっそく本にとりかかった。途中に1回だけ、長廻社長から、進捗についての問い合わせがあった。
約束通り、正月開けに原稿をお渡しして、その後、数回校正のための原稿のやりとりをした。
そして、2月20日に本になって発売されたのである。
出版社の方は多く連絡してこられると思うが、そのかたがたがみんな、それを本にしたいというホンモノの情熱とすばやい行動力と著者への信頼をもっているわけではない。
門戸を開けておくと、いつかそういう人と出会えるはずだ。
photo by Chiara Cremaschi
